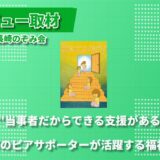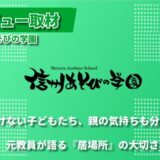『食べることは、生きること』を実感する機会が減りつつある現代。NPO法人食育研究会Mogu Moguは、食の向こう側にある生産者の思いや、食材が育つ過程まで含めた「本物の体験」を大切にしています。設立から21年、親子で楽しむ食育活動を通じて、次世代の食の担い手を育ててきた代表の松成さんにインタビューしました!

活動の原点 ―食べ物の向こう側を知る―
ー貴会の活動概要について、対象となる方や具体的な活動内容を教えていただけますか?
松成さん:私たちの活動は、主に子育て世代の親子を対象としています。すべてのプログラムは、親子で一緒に参加していただくことを基本としています。また、食育に関心のある一般の方や、教育関係者の方もお迎えしています。
活動の中心となるのは、体験型の食育プログラムです。市の公共施設にある菜園での農作物の栽培から、収穫した野菜を使った調理実習まで、「畑からテーブルまで」を一貫して体験していただいています。
料理教室も定期的に開催しており、和洋さまざまに、食材の特性や調理の基礎を親子で学んでいます。要請があればオンラインでのセミナーや、学校・企業向けの食育プログラムなども行っています。
特に力を入れているのが、和食の伝統文化継承です。米・魚・大豆という和食の基本を学ぶ機会を提供したり、地域の食文化や特産物について知っていただくワークショップなども実施しています。
活動頻度としては、定例の体験プログラムを2ヶ月に1回程度開催しています。講演などは、依頼に応じて随時行っています。
私たちの活動の特徴は、自然界から得られる原形に自分の体で触れる「一次体験」を重視していること。そして、「にこにこできる」「大体でいい」「いろいろある」という柔軟な姿勢を大切にしていることです。五感を使った体験的な学習を通じて、食の楽しさや奥深さを感じていただいています。
母親たちの「分からない」から始まった挑戦
ー食育研究会Mogu Moguを立ち上げたきっかけを教えてください。
松成さん:この活動は20数年前、子育て中の母親たちの「分からない」という声から始まりました。当時は手作りご飯、行事食、伝統の継承など、全て母親の責任とされていた時代だったのですが、実際には核家族で孤立した子育ての中で、どうしていいか分からない母親がたくさんいたのです。
そんな中地域の集会で出会った10人ほどの母親たちと「一緒に勉強しよう」と活動を始めました。最初は特産物を調べたり、小さな畑で野菜作りを始めたり。その後親子で参加できる料理教室をスタートさせ、徐々に活動の幅を広げてきました。
大切にしているのは「完璧を目指さない」という考え方です。分からないことは一緒に学び、失敗も含めて体験する。そんな思いで続けてきた活動が、今では食育の新しいカタチとして支持されています。
体験と五感で学ぶ、Mogu Moguメソッド
ーMogu Moguならではの特徴的な取り組みを教えていただけますか?
松成さん:私たちの活動には2つの大きな特徴があります。
1つ目は「一次体験の重視」です。テレビで見ただけの知識や、途中から参加する体験ではなく、すべての工程を自分の手で行っていただきます。例えば、こんにゃく芋をすりおろした時の手の痒みや、失敗して固まらなかった経験など、成功も失敗もすべて含めた実体験を大切にしています。
2つ目は「五味五感の教育」です。酸味や塩味、だしの味わいなど、素直に感じていただく機会を提供しています。美味しさは舌だけでなく、香りや見た目、音なども含めた総合的な体験です。そして最も大切なのは、「それぞれが違う感じ方をしていい」という価値観です。実際に、普段は授業で手を挙げない子どもたちが、自分の感じたことを積極的に発言してくれる姿が見られます。
次世代に向けた新たな挑戦
ー今後の展望について教えてください。
松成さん:現在、プロボノ活動を通じて、若い世代との連携強化に取り組んでおり、大学生のグループと協働し、SNSでの情報発信方法を見直すなど、現代のニーズに合わせた活動の展開を目指しています。
具体的には教育学や子育て、食物学に興味のある若い方々と問題意識を共有し、「カップラーメンは良くない」と言うだけでなく、「なぜ良くないのか」「どうすればいいのか」を一緒に考えていける仲間づくりを進めています。
また、今年度は助成金を活用して、和食の伝統伝承に力を入れています。単に「和食を食べましょう」「魚をもっと食べましょう」という単純な話ではなく、米・魚・大豆を軸とした日本の食文化と、小麦・肉・乳製品を基本とする西洋の食文化の違いを理解し、現代の生活様式に合わせた形で伝えていく取り組みを始めています。
にこにこ、大体、いろいろ ―食育を身近に―
ー最後に、読者へのメッセージをお願いします。
松成さん:「食育」という言葉は、どうしても堅いイメージや教育的な印象を持たれがちです。しかし私たちはニコニコできる食環境を目指し、楽しく良い思い出を作ることを心がけています。
参加者の方々には、メッセージのうち1つでも心に残っていただければと思っています。
食に関する新しいテーマやアイデアをお持ちの方は、ぜひご相談ください。また、独自のテーマをお持ちの方には、一緒に企画を作り上げていく仲間として参加していただければ嬉しく思います。「食の向こう側を知る」という私たちの理念に共感していただける方との出会いを、心待ちにしています。