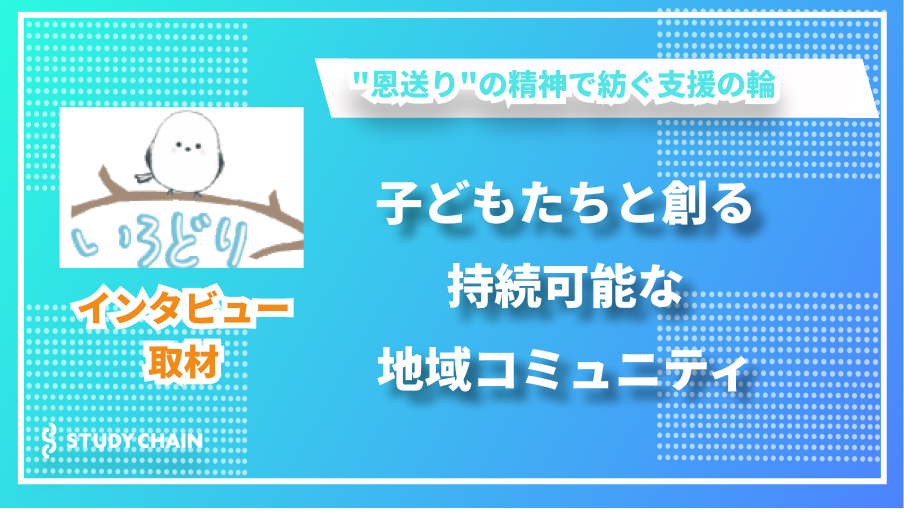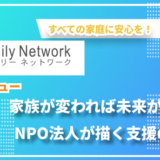東日本大震災のボランティア活動をきっかけに設立されたNPO法人いろどり・みんなのみち。地域福祉と和装文化を軸に、子どもから高齢者、外国人まで幅広い層に向けた活動を展開しています。
子どもたちの主体性を大切にした事業を展開する同法人の取り組みについて、浅野さんにお話を伺いました。
震災支援から始まった地域コミュニティづくり

ー団体の概要と、設立の経緯についてお聞かせください。
浅野:当法人は地域福祉、和装観光、まちづくりの3つを柱として、子どもから高齢者、外国人の方を対象に活動しています。
地域福祉の面では、着物の着付けボランティアを高齢者施設で行ったり、地域食堂でのサードプレイス作りを通じて、多世代交流の場を提供しています。
和装観光では、着物体験や街歩きプログラムを実施し、外国人観光客向けの日本文化体験を行っています。
まちづくりでは地域資源を活かした様々なイベントを展開し、お化け屋敷や子ども向け体験型カフェなど、大人も子どもも一緒に楽しめる企画を実施しています。
設立のきっかけは、東日本大震災発生時の2011年に遡ります。私が震災ボランティアとして宮城県石巻市で活動していた際、復興過程で様々なコミュニティの課題に直面しました。
情報格差や経済格差、独居老人の問題など、多くの課題がある中で、「誰もが安全で安心して過ごせる居場所が必要だ」という思いから、法人を設立しました。
震災支援を通じて、真の復興には継続的なコミュニティ支援が不可欠だと実感したことが、活動の原点となっています。
子どもたちの主体性を育む独自の取り組み
ー子ども向けの支援活動の内容について、詳しくお聞かせください。
浅野:2024年に立ち上げた「こども実行委員」が特徴的な活動です。未就学児から小学6年生まで39名が参加し、子どもたち自身が町の課題を見つけ、主体的に企画を考えてイベントを実施しています。
この活動を通じて、自己肯定感や自己有用感を育み、地域課題に向き合う社会的責任を意識してもらうことを目指しています。
子どもたちが「自分がお世話になった地域をもっと良くしたい」「こんな社会にしたい」という夢や目標を持ち、それに向かって行動できる人に育ってほしいという願いを込めています。
また、和装教育も特徴的な取り組みの一つです。コロナ禍以前は、小中学校で着物の歴史を学ぶ授業や着付け体験を行っていました。子どもたちに日本の伝統文化に触れる機会を提供し、お辞儀や作法なども含めた和の文化教育を実施しています。
直近では文化庁の助成事業で、日本舞踊と着物の着付け体験プログラムを実施し、小学生から高校生まで20名以上が参加しました。
ほとんどの子どもたちは着物についての知識がない状態で参加しますが、活動を通じて着物への興味を深め、より身近な存在として捉えられるようになっています。
歴史的な背景を含めて理解を深めることで、和装文化の継承にもつながっていると感じています。
ー活動において、子どもたちと接する際に意識していることはありますか?
浅野:私たちは、失敗を恐れずにチャレンジできる環境づくりを心がけています。「これはしてはいけない」という制限は極力設けず、失敗を通じて学べる機会を大切にしています。
子どもたちには必ず冒険心があり、その芽を摘むのではなく、失敗から学び、成長できる場を提供したいと考えています。子どもたち同士で反省し合い、次につながる成長の過程を重視しています。
子どもたちを「参画者」として位置づける支援活動
ー独自で行っている特徴的な取り組みについてお聞かせください。
浅野:最大の特徴は、子どもたちを単なる参加者ではなく、「参画する存在」として位置付けていることです。
イベントに参加して学ぶだけでなく、自分たちで企画を立て、大人と協働しながら実現していく。その過程一つひとつに意味があることを伝えながら、丁寧に活動を進めています。
今後は活動の幅を広げ、中高生向けの実行委員会も立ち上げる予定です。現在の小学6年生が進学後も継続して活動できる場所を作り、より幅広い年齢層での地域づくりを目指しています。
子どもたちの成長に合わせて活動の場を広げることで、持続可能な地域コミュニティの形成を目指しています。
「恩送り」の精神を未来につなぐ
ー最後に、記事をご覧の方へメッセージをお願いします。
浅野:私たちが最も大切にしているのは「恩送り」の精神です。ボランティアの本質は、受けた恩を次の人へと送ることにあります。
「ありがとう」の気持ちは相手に伝えながらも、その思いを別の誰かにも送っていく。NPOやボランティア活動を特別なものとせず、受けた「ありがとう」を自然な形で次の誰かに送れる社会。それが私たちの目指す姿です。
この「恩送り」の連鎖が、より豊かな地域社会を作り出すと信じています。