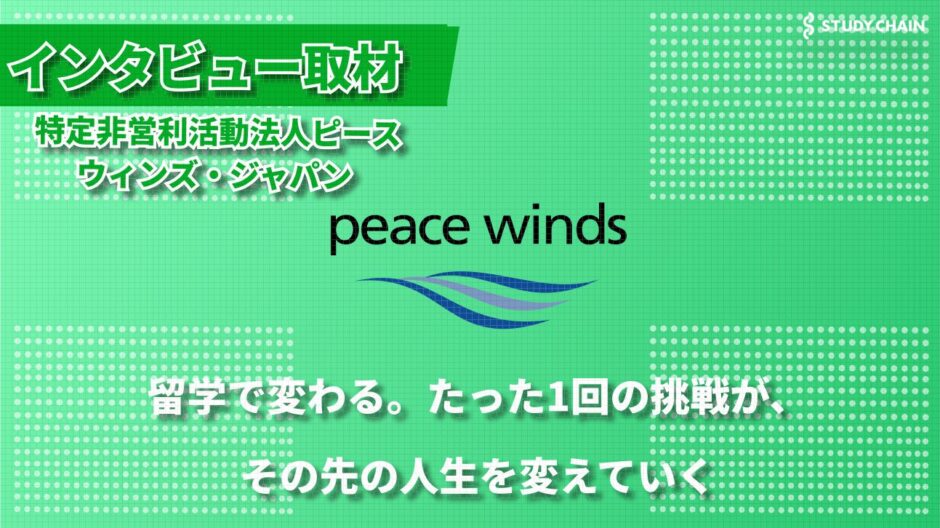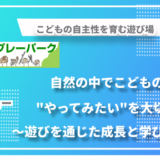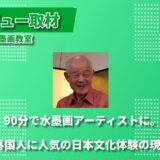2022年、一人の児童養護施設の子どもから『留学がしたい』という相談がありました。その声をきっかけに始まった支援は、今では多くの子どもたちの未来を変える可能性を持つプログラムへと発展しています。15名の参加者を輩出し、さらなる広がりを見せるpeace winds japanの取り組みについて担当者の中橋さんにインタビューしました!

児童養護施設の子どもたちの未来を広げる留学支援プログラム
ー御社の子ども支援事業について、具体的な活動内容を教えていただけますでしょうか。
中橋さん:当初は2017年頃から、難民キャンプや紛争地域の子どもたちを日本に招いてのサマースクールや留学支援を行っていたのですが、コロナ禍で一時中断を余儀なくされました。
その後、2022年に児童養護施設の子どもから「留学したい」という声があり、イギリスへの1年間の留学支援をスタート。これを機に、児童養護施設の子どもたちへの支援に注力するようになりました。2023年にはアメリカへの短期留学プログラムで6名の子どもたちを支援しています。
支援の原点と目指す未来
ー児童養護施設の子どもたちへの支援を始められたきっかけについて教えてください。
中橋さん:きっかけは、2022年にある児童養護施設の子どもから「留学がしたい」という一通の相談を受けたことでした。当時、私たちはそれまで児童養護施設の子どもたちに特化した支援は行っていませんでしたが、この声をきっかけに、この子のイギリスへの1年間の留学支援をスタートしました。
そして、支援を進める中で、児童養護施設の子どもたちが抱える様々な課題が見えてきました。高校卒業後の進路選択は非常に限られており、就職か働きながらの進学かという厳しい選択を迫られています。また、各家庭の事情や過去の経験など、一人一人が異なる背景を持っているにも関わらず、その選択肢は狭められているのが現状でした。
このような状況を目の当たりにし、私たちは「何か支援できることがあるはずだ」と考えるようになりました。奨学金の情報提供や、子どもたち自身が気づいていない可能性の発見をサポートすることで、彼らの選択肢を広げられるのではないか。特に、海外で同じような境遇から活躍している方々との出会いを通じて、新しい可能性に気づくきっかけを提供できるのではないか。
そうした思いから、2023年にはアメリカへの短期留学プログラムを実施し、6名の子どもたちの支援をスタート。児童養護施設の子どもたちへの支援を、私たちの重要な活動の一つとして位置づけるようになりました。
支援活動の特徴と強み
ー御社の支援活動における特徴や強みをお聞かせください。
中橋さん:多くの支援団体が「今日の食事」や「寝る場所」といった緊急性の高いニーズに対応する中、私たちは子どもたちの将来に焦点を当てた支援を行っています。もちろん、緊急支援も重要ですが、私たちは「その先」を見据えた支援を特徴としています。
具体的には、子どもたちが将来やりたいことを実現できる未来や、より多くの選択肢を持てる将来につながるような長期的な視点でのサポートを心がけています。例えば、留学支援を通じて海外で活躍する同じ境遇の方々との出会いを提供したり、奨学金などの進学支援の情報を提供したりすることで、子どもたちの可能性を広げる機会を作っています。
また、私たちの支援は単なる機会の提供に留まりません。子どもたち一人一人の思いに寄り添い、「本当はこんな夢を持っていた」「実はこういうことをやってみたい」という声を丁寧に拾い上げ、それを実現するための具体的なステップを一緒に考えていきます。
子どもたちの可能性を広げる支援姿勢
ー子どもたちと接する際に、特に意識されていることはありますか?
中橋さん:児童養護施設で育つ子どもたちの多くは、「これは駄目」「それは無理」といった否定的な言葉を多く聞いて育ってきた経験があります。もちろん、施設にはルールがあり、それ自体は必要なものです。しかし、私たちは子どもたちと接する際、できるだけネガティブな言葉は使わないように心がけています。
代わりに、子どもたちが目指したいことがあれば、それを実現するために現状からどのように変えていけばよいのか、一緒に考えるようにしています。子どもたち自身が持つ目標について、共に考え、寄り添うことを最も大切にしています。
留学支援がもたらす変化
ー実際に留学を経験した子どもたちに、どのような変化が見られましたか?
中橋さん:2024年に参加した子どもたちは、当初、自分の思いを表現することに消極的でした。しかし、留学を通じて大きく変化し、施設の先生に自分の思いを伝えられるようになりました。その結果、専門学校への進学を実現できた子もいます。また、グローバルな視点で将来を考えるようになり、「大学卒業後に留学して、海外で生活したい」という具体的な目標を持つようになった子どもたちも出てきています。
今後の展望
ー今後の活動についての展望をお聞かせください。
中橋さん:現在、SIA(Study in America)プロジェクトとして展開している留学支援プログラムでは、3年間で15名の参加者を輩出しています。
今後は参加者によるコミュニティを形成し、彼らが得た経験や知識を社会に還元していく循環を作りたいと考えています。また、2025年からは公募制を導入し、より多くの児童養護施設の子どもたちに機会を提供していく予定です。
児童養護施設の子どもたちへのメッセージ
ー最後に、この記事を読まれる方へのメッセージをお願いいたします。
中橋さん:現在、私たちが支援できる施設は全国の児童養護施設の4分の1程度に限られています。しかし、この活動を知っていただくことで、同じような境遇の子どもたちに「自分の行動一つで、選択肢が広がる可能性がある」ということを感じていただけたら嬉しいです。
まだ直接支援できない施設の子どもたちにも、これまでの参加者たちの体験や成長の様子を知っていただくことで、将来への希望を持っていただければと思います。一人一人の小さな一歩が、大きな変化につながる可能性を信じています。
※本プロジェクトの詳細や支援方法については、ピースウィンズ・ジャパンのウェブサイトをご覧ください。