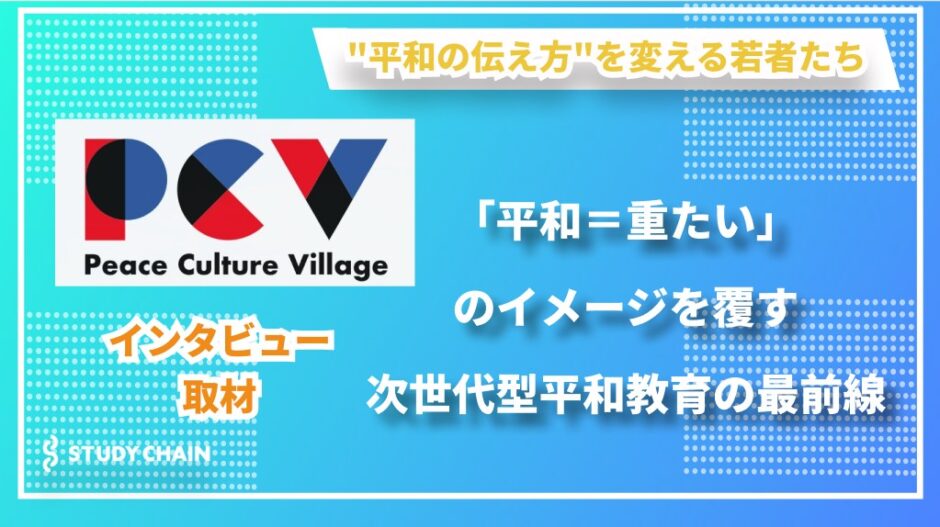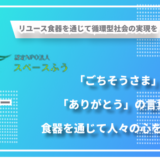広島の平和公園を訪れる修学旅行生の多くは、被爆の歴史を「学ぶ」という受動的な姿勢で臨みがちです。しかし、『NPO法人 Peace Culture Village(以下PCV)』は従来の平和教育とは一線を画す新しいアプローチを実践しています。10代20代の若いガイドメンバーと共に平和公園を巡り、対話を通じて平和について考える。そんな体験型の平和学習を提供し、注目を集めています。
「平和について考えることは難しくない」。そう語るのは、同法人で平和教育事業ディレクターを務める楢崎桃花(ならさき ももか)氏です。被爆者から直接体験を聞く機会が減少する中、テクノロジーを活用した伝承の取り組みや、オンラインでの平和教育プログラムなど、時代に即した多様な活動を展開。今回は楢崎氏に、『PCV』の活動内容や設立の経緯、そして未来への展望について詳しくお話を伺いました。
10代20代が案内する新発想の平和学習 ―『PCV』が行う3つの革新的事業

ー楢崎さま、本日はどうぞよろしくお願いいたします!まずは、『PCV』の事業内容について詳しくお聞かせください。
楢崎桃花 平和教育事業ディレクター(以下敬称略):『PCV』では主に3つの事業を展開しています。
1つ目は修学旅行生向けの平和公園ガイドツアーとワークショップの運営です。広島には毎年たくさんの修学旅行生が訪れますが、私たちは10代20代のガイドメンバーが10人程度の小グループで案内する「ピースダイアログ」というプログラムを実施しています。「ダイアログ(対話、対談)」という言葉に込められているように、対話を通じて共に学び合うことを大切にしています。
2つ目は「ピースカルチャーアカデミー(PCA)」というオンラインスクールです。半年間の期間限定で、日本全国からの参加者が自己探求のワークに取り組みます。「平和×〇〇」というフォーマットを使って、それぞれが平和についての考えをプレゼンテーションにまとめ、最後は対面での「ピースカルチャーフェスティバル」で発表します。「自分を知り、世界を変える」というコンセプトを軸に活動を展開しています。
3つ目はテクノロジーを活用したアプリ開発です。広島平和公園の画面上で原爆ドームをタップすると歴史的背景がナレーションで流れたり、被爆者の方のホログラムを通じて証言を聞くことができる機能を実装しています。被爆者の方から直接お話を聞く機会が減少している中で、映像や音声を通じて被爆体験を伝承していく取り組みを行っています。
設立の経緯と変遷
ー『PCV』が設立された経緯について教えていただけますか?
楢崎:『PCV』は2017年に、広島平和文化センター(「広島平和記念資料館」を運営する組織)の理事長を務めたスティーブン・リーパー氏によって設立されました。リーパー氏は同センターで初めての外国人理事長でした。
当初は広島県三次市甲奴町に拠点を置き、海外の方々と共に平和文化の村づくりを進めていました。しかし、金銭的な課題もあり、2019年に現在の専務理事である住岡健太氏が『PCV』に加わったことを機に、広島市内に活動拠点を移転。2020年秋からは現在の形である「ピースダイアログ」プログラムをスタートさせました。
設立から現在まで、活動形態は大きく変化していますが、「平和文化を一人一人の心の中で育んでいく」という設立時のビジョンは今も大切に引き継いでいます。平和文化を広めていくアプローチは変わっても、その本質的な価値は変わることなく受け継がれています。
「教える」から「対話する」へ ― 従来の平和学習を覆す新たなアプローチ

ー他のNPO法人との違いや、『PCV』ならではの特徴を教えてください。
楢崎:最大の特徴は「共に考える」というアプローチです。特に修学旅行生との関わりにおいて、一方的に教える従来の平和教育ではなく、対話を通じて共に考えることを重視しています。
10代20代のガイドメンバーが活動することで、参加する生徒との年齢が近く、友達のような関係性を築きやすいのも特徴です。また、「広島で活動している=広島出身者」というイメージを持たれがちですが、実際には大学進学を機に広島に来た若者も多くガイドとして活動しています。このことは、生徒さんにとって親近感を抱きやすく、「こういう平和へのアプローチもあっていいんだ」という気づきにもつながっているのではないでしょうか。
難しく考えすぎない平和教育、一緒に考えて平和とは何かを探求していく、そんなスタンスを常に意識しながら活動を展開しています。
「あなたにとっての平和とは?」― PCVが実践する革新的プログラムの全容
ー具体的な「ピースダイアログ」の内容について、より詳しく教えてください。
楢崎:基本的な「ピースダイアログ」のガイドツアーは1時間の平和公園巡りと15-20分の振り返りで構成されています。ツアー中はどうしても情報のインプットが多くなるため、最後に振り返りの時間を設け、生徒さんが感じたことや印象に残ったことを共有する機会を作っています。
特徴的なのは、ツアーの約半分を原爆投下前の暮らしに焦点を当てている点です。当時の広島県・中島地区の人々の日常生活を紹介することで、「私たちと同じような生活をしていた人々の身に起きた出来事」として原爆の被害を実感してもらいます。
振り返りの最後には「ツアーを通して考える、あなたが本当に大切にしたいものは何ですか?」という問いかけをしています。これは、当時の中島地区の人々も大切にしたいもの、失いたくないものがあったはずだという文脈から、今を生きる私たちにとっての大切なものを考えてもらうためです。
「ピースダイアログ」のワークショップでは、主に2つのプログラムを用意しています。
1つ目は大谷翔平選手が使用していたというマンダラート(81マスに目標に到達するまでの行動を埋めていくシンプルなフレームワーク)という手法を活用したもので、「平和な世界を作るために自分に何ができるか」をアイデア出しする取り組みです。
2つ目は、ガイドメンバーによる5分程度のプレゼンテーションです。各メンバーが「なぜ平和活動に携わっているのか」を発表することで、平和活動への多様なアプローチを紹介しています。
また、オンラインにて修学旅行の事前学習プログラムも行っています。オンラインの事前学習では、広島に来る前のマインドセットの時間として、まずは広島に興味を持ってもらうための時間作りをします。広島で起こったことが自分には関係ないことではなく、自分ごととして考えることができるような工夫をして授業を届けています。
活動への想いと海外からの反応
ー平和活動に携わるメンバーの想いは様々だと思いますが、どのような方が多いのでしょうか?
楢崎:本当に多様な動機を持ったメンバーが集まっています。広島出身のメンバーの中には、曽祖母や曽祖父が被爆者という方もいれば、家族に被爆者がいても当初は平和について特に関心がなかった人もいます。例えば、海外で「広島って今は住める場所なの?」「まだ放射能の影響が残っているんじゃないの?」と聞かれて答えられなかった悔しさから活動を始めたメンバーもいます。
私自身は高校生時代の国際交流がきっかけでした。海外の方々に平和公園を案内する機会があり、そこから徐々に平和について学び、伝えることの大切さに気づいていきました。このように、それぞれが異なる経験や想いを持って活動に参加しています。
ー海外からの参加者の反響はいかがですか?
楢崎:最近は海外の高校や団体からの依頼も増えています。「実際に広島に来て良かった」という声を多くいただきますが、特に印象的なのは復興の様子への驚きです。「まだ焼け野原なのでは」というイメージを持っている方も少なくありませんが、実際に街の復興を目の当たりにすることで、新たな気づきを得られているようです。
また、アメリカからの参加者は「アメリカのことを憎んでいますか?」といった率直な質問をすることもあります。そういった対話を通じて、互いの理解を深めていく機会にもなっています。

広島から世界へ ―全国に広がる新しい平和教育の波
ー今後の展望についてお聞かせください。
楢崎:平和について、より多くの人が気軽に考えられる機会を作っていきたいと考えています。まだまだ平和活動は「難しいもの」「自分にはできないもの」というイメージを持たれがちですが、私たちは必ずしも事業を大きくすることだけを目指しているわけではありません。むしろ、一人一人が当たり前のように平和について考えられるようなきっかけを提供し続けていきたいと考えています。
最近では長崎でも同様のプログラムが始まり、私たちも沖縄や長崎、鹿児島に同じような志を持った仲間と活動をしていくという予定があります。広島だけでなく、日本全国、そして世界各地に平和文化を広げていけるようなきっかけづくりを進めていきたいですね。それぞれの地域でネットワークが広がり、より多くの人が平和について考え、対話する機会が生まれることを期待しています。
「平和」は、もっと自由でいい。 ― ラストメッセージ

ー最後に、『PCV』への参加を検討されている方、そしてこのインタビュー記事で活動内容を知った方々へのメッセージをお願いします!
楢崎:もしかしたら、今の世界に対して悩みや不安を抱えている方もいらっしゃるかもしれません。でも、平和について考えることは、決して難しいことではありません。例えば、サッカーを通じて平和を考える、メンタルヘルスの観点から平和を考えるなど、アプローチは人それぞれです。私たちの過去のメンバーの中にも、そういった多様な視点から平和について考え、発信してきた人がたくさんいます。
一見、平和は難しいテーマに感じるかもしれませんが、まずは「自分にとっての平和とは何か」を考えることから始めてみませんか?そうすれば、誰にでも関わりのあるもの、日常の中から考えていけるものだと気づくはずです。その一歩が、やがて平和文化の輪を広げることにつながり、より良い世界づくりに貢献していくと信じています。
ぜひ一緒に、自分なりの平和について考えていけたらと思います。そこから平和文化の輪が広がり、世界がつながっていくことを願っています。