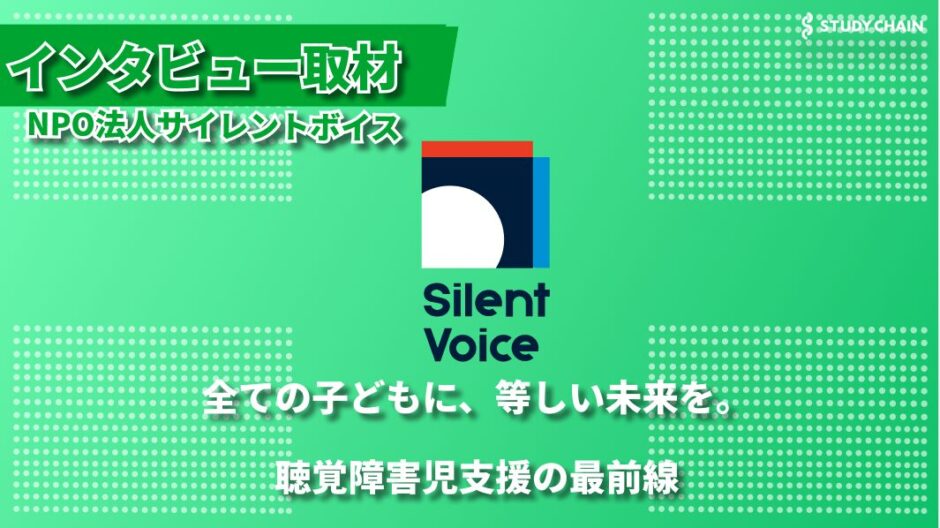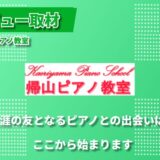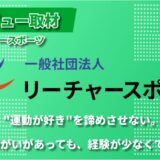「聴覚障害があっても、どんな未来も選択できる」。そんな思いを胸に、NPO法人サイレントボイスは聴覚障害のある子どもたちの支援に取り組んでいます。全国でわずか20か所ほどしかない聴覚障害児特化型の放課後等デイサービスの運営や、オンラインでの遠隔支援など、独自の視点でサービスを展開。今回はNPO法人サイレントボイスの取り組みについて、同社教育事業にて言語聴覚士として働く平松さんにインタビューしました!
NPO法人サイレントボイスの事業内容
ーNPO法人サイレントボイスの主な事業内容について教えてください。
平松さん:NPO法人サイレントボイスでは主に3つの事業を展開しています。1つ目は、聴覚障害者を雇用する企業対象のコンサルティング事業「デフビズ」です。聞こえる、聞こえないの違いを相互理解する研修、職場改革に向けた実践計画の伴走支援をしています。
ろう難聴者と聴者がともには働くサイレントボイスならではの解説と手法で職場に新しい活躍を作り出しています。2つ目が、聴覚障害のある子どもたちのための放課後等デイサービス「デフアカデミー」です。聴覚支援学校や地域学校(難聴学級)の小・中・高校生を対象に、集団授業やイベントを実施し、居場所と成長の場の提供を行っています。
もう1つの事業は、オンライン教育事業「サークルオー」です。これは完全にオンライン上で聴覚障害のある子どもたちの学習支援や言語支援を行うプログラムです。身近に支援地域のないご家庭からの要望をきっかけにサービスが立ち上がり、現在4年目を迎えています。
当初は、コロナ禍による外出制限下で、子どもたちの孤立を防ぐため、各種助成金を活用して無料でサービスを提供していました。現在は一定の利用料をいただきながらサービスを継続していますが、オンラインでの遠隔支援を既存の福祉制度に組み込んでもらえるよう、こども家庭庁に働きかけを行っています。
サイレントボイスの特徴
ー他の支援施設との違いや特徴について教えてください。
平松さん:最大の特徴は、企業研修部門「デフビズ」との連携により、総合的な支援が可能な点です。例えば、「デフビズ」ではろう者の方々に向けた職場定着プログラムを提供しており、教育支援から就労支援まで幅広いサポートが可能です。
さらに、無言語コミュニケーション研修「DENSHIN」というプログラムでは、聞こえる人に対して、音のない環境でコミュニケーションを体験する機会を提供しています。これらの大人そして社会に対する取り組みは、教育支援に特化した他の施設にはない特徴だと考えています。
聴覚障害者とのコミュニケーション方法
ー実際に聴覚障害をお持ちの方とのコミュニケーション手段について教えてください。
平松さん:現在は環境が大きく変化してきています。まず補聴器についてですが、これは単純に音を大きくするだけではなく、個々の聴力に合わせて細かな調整が可能な機器です。
それとは別に人工内耳という選択肢もあります。これは耳の中に細い電極を入れて神経に直接電気信号を送り、音を届けるという方法です。人工内耳の手術を受けた子どもたちは調整や訓練後、音声でコミュニケーションを取ることも多いですが、聞こえにくさは残るため、手話も併用している子どもたちもいます。
補聴機器を使用せず完全に手話のみでコミュニケーションを取る子どもたちもいます。音声で表現しても、情報の受け取りは手話が中心という方もいます。このように、コミュニケーション方法は個人によって様々です。

利用者と接する際に意識していること
ー支援の際に特に気をつけていることはありますか?
平松さん:最も重視しているのは、個々の子どもに合わせたコミュニケーション方法の選択です。
支援に際しては、その子どもが最も快適にコミュニケーションを取れる方法を見極め、必要に応じて環境調整を行います。また、子ども一人一人の成長段階や興味関心に合わせた支援プログラムを提供することも大切にしています。
聴覚障害児が直面する課題
ー聴覚障害をお持ちの方々が直面している課題について教えてください。
平松さん:最も大きな課題は孤立です。聴覚障害児は1000人に1人程度しかおらず、支援学校も限られています。例えば大阪でも聴覚支援学校は3つしかありません。そのため、遠方から通学する必要があったり、人工内耳を使用している子どもが地域の小学校に通う場合、難聴への理解が十分でない環境に置かれることもあります。
また、同じような境遇の子どもたちと出会う機会も限られています。支援学校でも1学年10人に満たないケースもあり、ロールモデルとなる先輩や同級生との出会いも少ないのが現状です。
コロナ禍では外出が制限され、さらに孤立が深刻化しました。そのような状況下で、オンラインによる支援事業「サークルオー」を立ち上げ、「一人じゃない」という思いを伝える活動を続けています。
今後の展望
ー今後の活動についてどのようなビジョンをお持ちですか?
平松さん:現在、最も力を入れているのは、オンライン支援の制度化です。「サークルオー」の活動を通じて、オンラインでも効果的な支援が可能だということが実証できました。これを福祉制度の一環として組み込んでいただけるよう、働きかけを行っています。
また、職域の拡大も重要な課題です。AIによる音声のテキスト化技術の進歩や、タブレット端末の普及により、聴覚障害者が活躍できる場は確実に広がっていますが、私たちは、こうした可能性を子どもたちに早い段階から伝え、将来の選択肢を広げていきたいと考えています。
メッセージ
ー最後に、記事を読まれる方へメッセージをお願いします。
平松さん:なかなか接する機会のない、聴覚障害の子どもたちのことを想像するのは難しいかもしれませんが1000人に1人いるのです。どんな子どもにも等しくコミュニケーションが取れる場があること、そこから生まれる子どもたちの豊かな時間と成長を、ぜひ応援していただければと思います。
また、お子様が聴覚障害をお持ちで支援を求めている保護者の方々は、ぜひお問い合わせください。現在、東京を中心に全国にネットワークを持っており、地域に関係なくサポートができる体制を整えています。遠方の方でもオンラインでの支援が可能ですので、お気軽にまずはご相談いただければと思います。