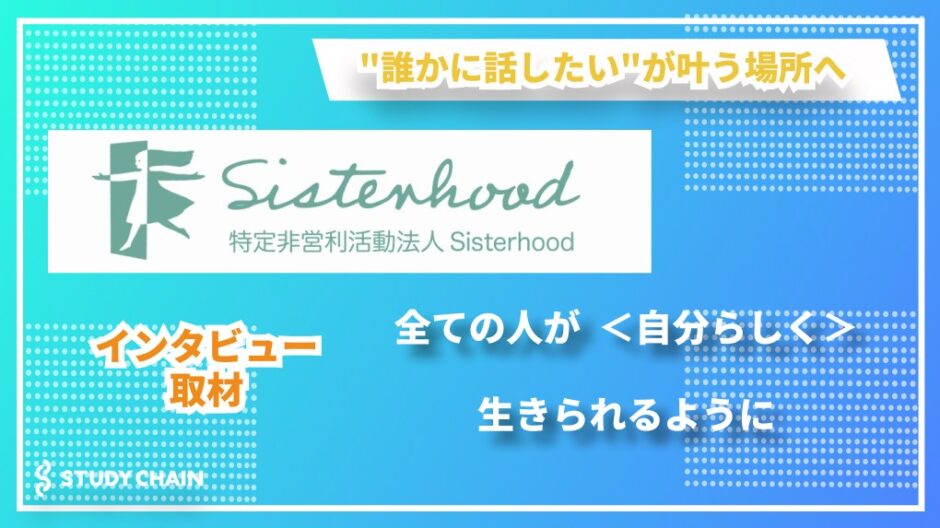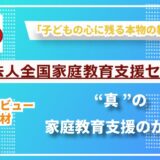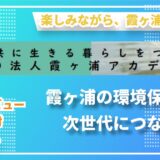近年、地方における若年女性の支援体制の整備が課題となっています。特に、家庭内でのケア労働や進路の制限、ハラスメントや職場での人間関係、キャリア形成など、女性特有の悩みに対応できる場所が限られているのが現状です。
そんな中、山形県で注目を集めているのが、『NPO法人Sisterhood(シスターフッド)』の取り組みです。同法人は、18歳から35歳までの若年女性を対象に、安心して過ごせる居場所づくりと支援活動を展開しています。
代表理事の小笠原千秋氏は、自身も地方で女性として生きる中で経験した困難から、「安心して話せる場所」の必要性を痛感したといいます。「なければ自分で作る」という決意のもと立ち上げられた同法人は、フリースペースの運営や支援者向け学習会の開催など、多角的なアプローチで女性支援に取り組んでいます。
今回は小笠原氏に、団体設立の経緯から今後の展望まで、詳しくお話を伺いました。

誰もが安心して過ごせる居場所づくりを目指して

ー小笠原さま、本日はどうぞよろしくお願いいたします!まずは『NPO法人Sisterhood(シスターフッド)』の概要について教えていただけますか?
小笠原千秋 代表理事(以下敬称略):私たち『NPO法人Sisterhood』は、女性支援を中心に活動している団体です。特に、地域社会の中で生きづらさを抱えている方々に対して、安心できる居場所と学びの機会を提供することを目的としています。
現在、主に2つの活動を展開しています。
1つ目は、若年女性向けのフリースペース「mayflower(メイフラワー)」の運営です。毎週木曜日と金曜日の16時から20時まで開設し、18歳から35歳までの性自認女性、Xジェンダーの方、ノンバイナリーの方にご利用いただいています。
利用者の方々は実に様々な背景をお持ちです。不登校を経験された方、就職に向けて一歩を踏み出せないでいる方、LGBTQ+等性的マイノリティとして悩みを抱える方、職場での人間関係に課題を感じている方など、それぞれの事情や悩みを抱えながら来所されています。
2つ目の活動は、支援者向けの学習会です。毎月第4日曜日の午前中に開催し、女性支援や居場所づくりに関する知識やスキルを学ぶ機会を提供しています。こちらは年齢制限を設けず、支援に関心のある方であればどなたでもご参加いただけます。

このように、直接的な居場所の提供と、支援の質を高めるための学びの場という、2つの側面から活動を進めています。
自身の経験から見出した使命
ー小笠原さまが『Sisterhood』を立ち上げられたきっかけを教えてください。
小笠原:私は約20年間社会人として働いていましたが、その中で職場でのハラスメントを経験しました。上司に相談しても十分な理解が得られず、かえって「相談したこと」で居づらい状況になってしまう、いわゆる二次被害のような経験もしました。
そうした経験を通じて、「安心して本音を話せる場所」の重要性を身をもって感じました。特に地方では、職場での悩みや生きづらさを相談できる場所が限られています。相談窓口はあっても、実際に足を運ぶまでの心理的ハードルが高かったり、形式的な対応に留まってしまったりすることも少なくありません。
「山形に、女性たちが気軽に立ち寄れる場所が必要だ」。そう考えた時、「なければ、自分で作るしかない」という決意が生まれました。最初は手探りの状態で、コロナ禍の影響もあってオンラインでの活動からのスタートでした。しかし、実際に活動を始めてみると、同じような悩みを抱える女性が予想以上に多くいらっしゃることが分かりました。
特に印象的だったのは、「こういう場所を探していた」「やっと話せる場所が見つかった」という声をいただいたことです。自分の経験が、決して特別なものではなく、多くの女性たちが同じように感じていた課題だったのだと気づかされました。そこから、オンラインでの活動に加えて、実際に集える場所の開設や、様々な講座の企画へと活動を広げていきました。
活動の原動力となる想い
ー小笠原さまの活動への想いの源泉を教えてください。
小笠原:私自身、地方で女性として生きていく中で、多くの理不尽な経験をしてきました。例えば、家族の中で男兄弟が優先され、大学進学の機会を得られなかったり、地域から出ることができなかったりした経験があります。
そして、驚くことに、現在もなお同じような悩みを抱える若い女性が多くいることを日々の活動の中で実感しています。地方からの若年女性の流出が問題視される中、一人一人が望む進路を選択できる環境づくりに貢献したいという思いが、活動の原動力となっています。
女性に特化した支援の意義

ー『Sisterhood』の特徴やアピールポイントを教えてください。
小笠原:山形では女性に限定した居場所づくりは、まだまだ珍しい取り組みです。確かに若者向けの居場所は数多くありますが、そういった場所では男性の利用者が多くなる傾向があり、女性の方々が安心して過ごせる環境を作ることが難しい現状がありました。
特に大切にしているのは、「安全な空間」の確保です。例えば、職場でのジェンダーに関する悩みや、性的指向・性自認に関する相談は、どのような考え方の人がいるかわからない空間では話しづらいものです。また、家族や恋愛関係の悩み、将来のキャリアについての不安なども、受け止めてくれる人がいるとわかっているこそ打ち明けられる内容が多くあります。
また、年齢を18歳から35歳に限定していることも、大きな特徴です。この年代設定により、就職、結婚、出産、キャリアの変更など、人生の大きな選択に直面する時期の女性たちが、互いの経験を共有し、支え合える関係を築くことができています。世代が近いからこそ、価値観を共有しやすく、より具体的なアドバイスや情報交換ができる環境が自然と生まれています。
特に、年上の方が「先輩風を吹かせたくなる」ような状況を避けられるのも、この年齢設定のメリットだと考えています。若い方々にとっては、親世代から同じような助言を受けて嫌な思いをした経験もあるかもしれません。同世代での対話の方が、より自然な形で経験を共有できる場合が多いように感じています。
寄り添う支援を目指して

ー利用者の方に接する際に、特に意識されていることはありますか?
小笠原:私たちが最も大切にしているのは、「共に在る」という姿勢です。支援者と利用者という関係性は避けられない部分もありますが、できるだけ権力性のような要素を排除し、同じ目線で一緒に考え、一緒に歩んでいけるような関係性を築くことを心がけています。
例えば、利用者の方が悩みを話してくださった時、つい「こうすればいいのに」とアドバイスしたくなる気持ちを抑えるようにしています。なぜなら、その方の人生や状況を一番よく知っているのは、その方自身だからです。私たちの役割は、解決策を提示することではなく、その方が自分の気持ちや考えを整理し、自分なりの答えを見つけられるようサポートすることだと考えています。
また、「居場所」という言葉の持つ意味を大切にしています。カウンセリングルームのような相談に特化した場所ではなく、お茶を飲みながらゆっくりと過ごせる、まるで友人の家に遊びに来たような雰囲気づくりを心がけています。時には黙って本を読んでいるだけの方もいれば、スタッフや他の利用者と会話を楽しむ方もいます。その日の気分で過ごし方を選べる自由さも、私たちの場所の特徴です。
もちろん、専門的なサポートが必要だと感じた場合は、適切な支援機関をご紹介することもあります。その際も、「ここではダメでした」という結論ではなく、「より専門的なサポートを受けられる場所がありますよ」という前向きな橋渡しを心がけています。私たちは地域の様々な支援機関と連携を取っており、その方に最適な支援につなげられる「入口」としての役割も担っています。
特に印象的なのは、利用を始めた当初は他の人と関わることを躊躇していた方が、少しずつ自分の気持ちを話せるようになり、やがて他の利用者の話に耳を傾け、支え合う関係を築いていく様子です。こうした変化は、決して私たちが主導したものではなく、その方自身の中で自然に生まれたものです。このような「自然な成長」や「関係性の広がり」を見守れることも、私たちの活動の醍醐味だと感じています。
新たなサービスの展開
ー今後の展望について教えてください。
小笠原:NPOとして大きな課題となっているのが資金面です。現在は大きな助成金をいただいて場所とスタッフを確保できていますが、これは期限付きのものです。
そこで、2025年からは自立的な運営を目指し、新しい取り組みとしてベビーシッター付きの家事代行サービスを開始する予定です。現在はモニター募集の段階ですが、このサービスを軌道に乗せることで、団体の持続可能な運営を実現したいと考えています。
また、女性学生支援の一環として、月2回、共同で夜ご飯を作って食べる「みんなで作ろう夜ごはん会」も開催しています。これは、奨学金とアルバイトで学費と生活費を賄っている学生さんとの出会いがきっかけで始めた活動です。昨今の物価高騰もあり、学生の生活支援の一助となればと考えています。このような活動も、認知を含めて、拡大していきたいですね。
気軽に立ち寄れる場所に

ー最後に、『Sisterhood』の利用を検討されている方へメッセージをお願いします!
小笠原:「話を聞いてもらいたい」「誰かと一緒にいたい」「何となく心が疲れている」。そんな小さな気持ちでいいんです。深刻な悩みがなければいけない、相談事がなければいけないということは全くありません。
弊団体の居場所スペース「mayflower」は、まるでお気に入りのカフェに立ち寄るような気軽さで使っていただける場所を目指しています。お一人でゆっくり本を読んでいただいても、スタッフや他の利用者の方とおしゃべりを楽しんでいただいても構いません。その日の気分で、過ごし方を選んでください。
私自身、地方で女性として生きていく中で、様々な理不尽さや生きづらさを感じてきました。「誰かに話したい」けれど「話せる場所がない」。そんな経験は、意外と多くの方が持っているのではないでしょうか。
でも、同じ想いを持つ仲間がいること、あなたの気持ちを受け止める場所があることを、ぜひ知っていただきたいと思います。たった一人で抱え込まなくていい。誰かと話すことで、気持ちが少し楽になることもある。そんな小さな、でも大切な一歩を踏み出すお手伝いができればと思っています。
「mayflower」という名前には、「希望」という花言葉の想いが込められています。あなたらしい人生の花を、一緒に探していけたら嬉しいです。どうぞ気軽に、お立ち寄りください。