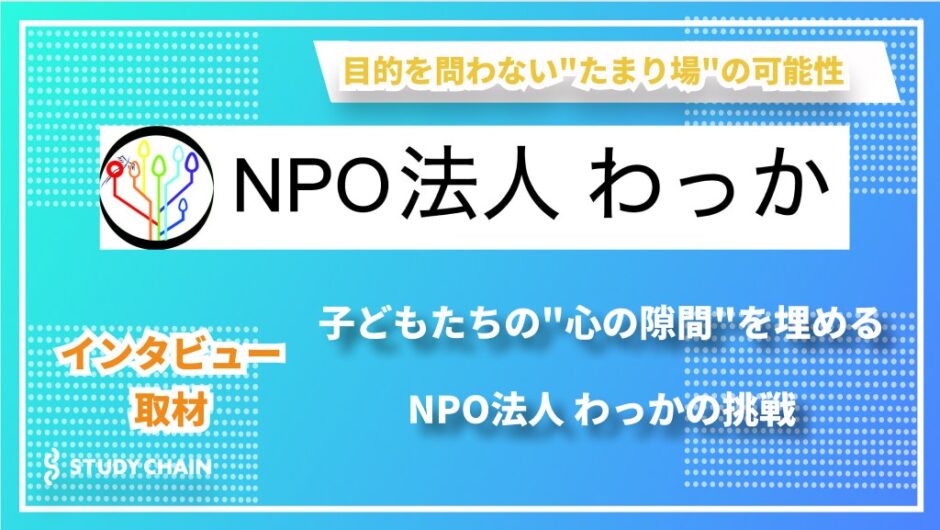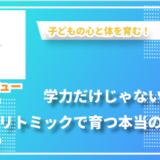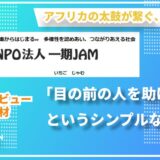少子高齢化や核家族化が進む現代社会において、子どもたちの居場所づくりは重要な課題となっています。特に、学校や習い事以外で、子どもたちが気軽に立ち寄れる場所が減少している現状は、子どもたちの健全な成長に影響を与えかねません。
そんな中で、滋賀県米原(まいばら)市で10年以上にわたり、子どもたちの居場所づくりに取り組んでいる『NPO法人 わっか』があります。古民家を開放し、子どもたちが自由に過ごせる空間を提供する一方で、必要に応じて学習支援や生活支援も行うなど、柔軟な支援活動を展開しています。
今回は、『NPO法人 わっか』である代表の柳生 のび氏に、活動への想いや、居場所づくりに込めた理念、そして今後の展望についてお話を伺いました。子どもたちの「ありのまま」を受け入れ、寄り添い続ける『わっか』の取り組みから、地域における子どもの居場所づくりの在り方を考えます。
「目的がなくても、ここにいていい」― 自由な居場所づくりへの挑戦

ー柳生さま、本日はどうぞよろしくお願いいたします!『NPO法人 わっか』ではどのような方を対象に、どのような活動を行われているのでしょうか?
柳生 のび代表(以下敬称略):『わっか』のメインテーマは「居場所づくり」です。対象は主に子どもたちですが、法的な定義での18歳未満に限定せず、若者も含めた広い意味での「子ども」を対象としています。
特徴的なのは、特定のコンテンツを提供するというよりも、来た子どもたちが自由に過ごせる場を作ることに重点を置いていることです。現代社会では、どうしても、目的がないと行けない場所が多くなっています。そういった場所も素晴らしいのですが、理由なくふらっと立ち寄れる場所というのも非常に重要だと考えています。
滋賀県米原の小さな町で、古民家を開放する形で細々とではありますが、そのような活動を続けています。10年ほど活動を続ける中で、来る層も変化してきました。特にコロナ禍を境に大きく変わりました。設立当初は共同代表ともう1人で始めた活動でしたが、現在は私が代表を務めています。
「友達の家に遊びに行くような気軽さで」― 誰もが心地よく過ごせる空間を目指して
ー実際には、どのような方々が『わっか』を利用されていますか?
柳生:活動を始めて10年の間に、来館者の層は大きく変化してきました。当初は未就学児を連れた親子連れや小学生が中心でしたが、コロナ禍を経て様子が変わってきています。特に、以前から来ていた子どもたちが成長して、今は中学生になっても足を運んでくれています。友達を連れて来てくれることも多く、最近は若干むさ苦しい雰囲気になっているくらいです(笑)。
私たちの活動の特徴は、様々な困り感を抱えた子どもたちを支援する一方で、敢えてそこに線引きをしないということです。ハードルを作らない形を選択しているので、そこに居てもその子が困難を抱えているということが分からないような場所になっています。
「行きたくても行けない子どもたちのために」― 『わっか』が歩んできた道のり
ー『わっか』を立ち上げられた経緯について教えてください。
柳生:NPO法人の立ち上げは、実は、必要に迫られてという部分が大きかったです。児童クラブ(学童保育)の委託業務も行っており、それを受託するにあたってNPO法人格が必要だったというのが一番の理由です。また、NPO法人格を持つことで寄付のお願いがしやすくなり、様々な補助金や助成金の申請も可能になります。活動を必要とする子どもたちのために長期的な活動を見据えて、法人格を取得しました。
私は以前から自然体験プログラムや森のようちえんなど、子どもに関わる様々な活動に参加してきました。それらの活動は非常に素晴らしいものですが、参加費用が必要なため、行きたくても行けない子どもたちがいることに気づきました。
そういった子どもたちも来られる場所を作りたいと考えていた時に、既に居場所づくり活動を行っている方々の話を聞く機会がありました。この形であれば、誰もが気軽に来られる場所が作れると確信し、活動を始めることにしました。
「その子に必要なものを、必要な時に」― 柔軟な支援体制が生み出す可能性

ー他のNPO法人にはない『わっか』ならではのアピールポイントを教えてください。
柳生:私たちの最大の強みは「柔軟性」だと考えています。居場所づくりがメイン活動ではありますが、様々な出会いの中で生まれた必要性に応じて活動の幅を広げてきました。
例えば、家庭が落ち着かず勉強ができない子どものために寺子屋を開いたり、帰宅したくない若者のために一時的な居場所を提供したり、生活面での支援や各種手続きのサポートなども行っています。個別のニーズに対して必要に応じてすぐに動ける、この「小回りの利く」対応力が私たちの一番のアピールポイントではないかと思います。
「まずは、その場にいること」― 独自の寄り添い方で子どもたちの成長を見守る
ー子どもたちと接する際に、特に意識されていることはありますか?
柳生:私たちの基本的なスタンスは、「その場に一緒にいる」ということです。グイグイと関わっていくのではなく、その場に共にいることを大切にしています。
初回はほとんど会話をせず、3回くらい来てようやく名前を聞くような、非常にゆっくりとした関わり方を心がけています。これが良いのか悪いのかは正直分かりませんが、このような人とのコミュニケーションの形もあると考え、大切にしています。
子どもたちから主体的に話しかけてくれるのを待つというスタンスを取っています。人が周りにいるだけで安心できる、そんな空間を作ることを重視しています。一人じゃないという感覚が、どれだけ子どもたちの心の支えになるか、私たちは日々実感しています。
「子どもたちの”やりたい”を大切に」― 多様な活動で広がる可能性

ー『わっか』で提供されているサービスについて、具体的に教えてください。
柳生:基本的には古民家の開放による「子どもたちの居場所づくり」が中心です。補完的に児童クラブの運営も行っています。
設備面では、WiFiやテレビゲーム、パソコンなども用意しています。特に中高生はWiFiがある方が立ち寄りやすいですし、ゲームも家では自由に遊べない子もいるので、にぎやかしとして置いています。
子ども食堂も実施していますが、これについては複雑な思いがあります。地域からの要望で始めましたが、「貧しい子が行く所」という偏見が子どもたち自身から聞かれることもありました。そのため、子ども食堂という形はあまり好んでいませんが、来やすさを考慮して活動メニューの一つとして継続しています。

スタッフは私を含めて3人のメインスタッフと、その都度お手伝いいただくボランティアの方々で運営しています。教員免許を持つスタッフもおり、寺子屋などの学習支援でその経験を活かしています。
子どもたちの主体性を重視し、お泊まり会やポケモンカード大会など、子どもたちが「やりたい」と言い出したことをできる限り実現できるよう支援しています。これにより、子どもたちの居場所への愛着も深まっているように感じます。
新たな拠点作りへの挑戦
ー今後、強化していきたい点や新たに取り組みたいことはありますか?
柳生:10年以上一カ所で活動を続けてきましたが、そろそろ2拠点目の開設を考えています。現在児童クラブを運営している地域の子どもたちとも7年ほどの付き合いがあり、強い繋がりができています。児童クラブの子どもたちが、放課後に「遊ぼう」「お茶しよう」と気軽に立ち寄ってくれるようになりました。
しかし、児童クラブという事業の性質上、登録していない子どもたちを受け入れることは難しい状況です。そこで、そういった子どもたちも集まれる新しい場所を作りたいと考えています。
米原市全体では人口減少傾向にありますが、私たちが活動している地域は珍しく人口が増加している地域です。この地域にもう一つ拠点を作ることで、より多くのニーズに応えられると考えています。来年度中(現在2025年)の実現を目指して準備を進めているところです。
「実際に会って、触れ合って」― デジタル時代だからこそ大切にしたいこと
ースマートフォンやSNSが普及する中で、リアルな居場所の重要性についてどのようにお考えですか?
柳生:今の子どもたちは、本当にきつきつのスケジュールで生活している印象があります。SNSでのコミュニケーションも楽しいものですが、やはり生身の人間との関わりから得られるものは別物だと考えています。
実際に顔を合わせ、共に時間を過ごす中で、新しい友達関係が生まれたり、異なる年代の子どもたち同士の交流が生まれたりしています。そういった予期せぬ出会いや関係性の広がりは、オンラインだけでは得られない貴重な経験だと思います。
「誰かがそっと見守っている」―『わっか』が作り続ける居場所

ー最後に『わっか』へ遊びに来たいと考えている方々へメッセージをお願いします!
柳生:『わっか』は、良い意味での「現実逃避」ができる場所です。勉強や部活、習い事で毎日頑張っている子どもたちが、時にはただボーッとしていたり、友達とダラダラ過ごしたり。そんな時間を過ごせる場所が、今の時代には必要だと思っています。
難しく考えずに、ほっとしたい時、ゆっくりしたい時に来てください。特別な理由はいりません。ただそこにいるだけで、誰かがそっと見守っている。そんな場所として、これからも地域の子どもたちの居場所であり続けたいと思います。