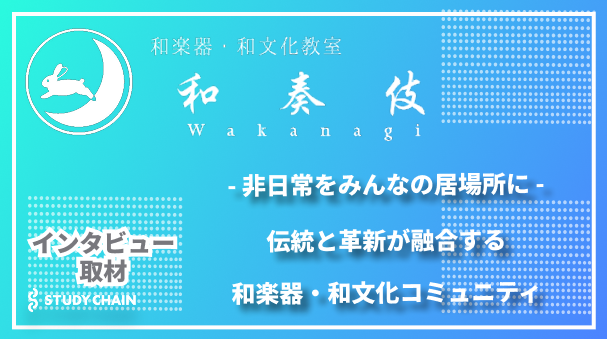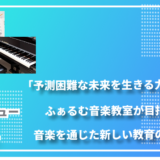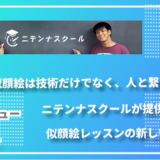三味線、箏、篠笛など8つの和文化を通じ、会員様の非日常な場所を展開する教室「和奏伎(わかなぎ)」。
伝統を大切にしながらも、現代的なアプローチで和文化の魅力を伝え、45歳前後という比較的若い世代を中心に150名以上の生徒が通う人気のコミュニティとなっています。
今回は、代表の藤本秀摂浩さんと藤本摂浩澪さんに、教室の特徴や魅力についてお話を伺いました。
教室概要

ー和奏伎ではどのような教室を展開されているのでしょうか?
藤本摂浩澪さん:和奏伎では、三味線、舞踊、箏、篠笛、鳴り物、落語、書道、着付けと、8つの和の教室を展開しています。
和奏伎の特徴として、各教室が独立しているのではなく、互いに連携を取り合い、協力し合える体制を整えています。
例えば、講師同士が気軽に「この曲を演奏するのですが、一緒にしませんか」と声を掛け合える関係性が築かれています。
会員様の年齢層は小学生から定年後のセカンドライフを楽しむ世代まで幅広く、平均年齢は45歳前後と、和文化教室としては比較的若い層が中心となっています。
会員様の年齢層は小学生から定年後のセカンドライフを楽しむ世代まで幅広く、平均年齢は45歳前後と、和文化教室としては比較的若い層が中心となっています。
設立の経緯・きっかけ
ー教室を始められたきっかけについて教えてください。
藤本秀摂浩さん:23歳で師範になり、27歳の時に10人ほどの生徒からスタートした三味線教室が始まりでした。
その後、楽器ごとに教室が別れている「縦割り」に疑問を感じ、様々な和楽器・和文化の講師を募集。
現在では三味線教室だけでも90名ほど、全体で150名以上の会員様が在籍しています。
「堅苦しいイメージの伝統芸能ではなく、伝統は大切にしながらも今風にアレンジする」という考えが、多くの会員様の支持を集めることになりました。
入会のきっかけも様々で、「YouTubeで和楽器演奏を見て興味を持った」「落語が好きで出囃子を自分でも演奏してみたいと思った」といった現代的な動機が目立ちます。
また、コロナ禍では「家にあった祖母の三味線を大切に使いたい」という想いで始める方もいらっしゃいました。
特徴やアピールポイント

ー和奏伎の魅力やアピールポイントを教えていただけますでしょうか?
藤本摂浩澪さん:和奏伎の最大の特徴は、「非日常」をコンセプトに「みんなの居場所」を作り出していることです。
通常の仕事や日常生活とは異なる自分を表現できる場として、会員の皆さんに愛されています。
また、公民館での演奏や高齢者施設への慰問、インバウンド向けの和楽器演奏など、対外的なイベントにも積極的に参加しています。
また、参加者のレベルに合わせてプログラムを組むなど、全員が楽しめる工夫も行っています。
藤本秀摂浩さん:教室運営面では、スマホアプリを活用した出欠管理やPDF教材の共有など、先進的な取り組みを行っています。
月1、2回のお稽古で顔を合わせる機会は限られていますが、スマホアプリでコミュニケーションを取り、資料や教材もクラウドで共有する。
アナログな伝統文化とデジタルの融合を実現している教室は、数少ないと思います。
生徒に指導する際に意識していること

ー指導の際に大切にされていることはありますか?
藤本秀摂浩さん:「非日常を楽しんでいただく」「楽しく長く続けていただく」ことを第一に考えています。
また、三味線教室では教育実習制度を設け、講師陣が日々研鑽を積むことで、誰が教えても均一な指導ができる体制を整えています。
基礎レッスンはマンツーマンで丁寧に指導し、その後は団体レッスンに移行するという段階的な指導方法を採用しています。
さらに、オンラインレッスンも取り入れており、海外(香港、アメリカ、ドイツ)からの受講生も在籍しています。
発表会では800人を超える観客の前で、習得した技術を実践できる演奏の機会も提供しています。
コースや料金体系について

ーレッスン時間はどのように設定されていますか?
藤本摂浩澪さん:マンツーマンレッスンは1時間、団体レッスンは2時間を基本としています。
また、初心者の方でも安心して始められるよう、楽器のレンタルも行っています。
8の教室があることで、複数の教室を掛け持ちする生徒が多いのも和奏伎の特徴です。
「三味線を始めたら着物も着てみたい」「落語の発表会で着物を着るために着付けを習い始めた」など、和の文化を総合的に学ぶ会員様も多く、最も多い方は4つの教室を掛け持ちされています。
今後のビジョン・展望

ー今後の展望についてお聞かせください。
藤本秀摂浩さん:指導者育成に力を入れており、特に若い世代の育成に注力しています。
私も自分の師匠より20歳若い世代なので、次の世代への伝承することを使命だと考えています。
和楽器は特別な人しかできないものではなく、誰でも楽しめるものだということを示していきたいです。
また、語学が堪能な生徒を和楽器の指導者として育成することで、グローバルな展開も視野に入れています。
オンラインレッスンの普及により、世界中どこからでも和楽器を学べる環境が整っていますので、多言語で指導できる人材育成を目指しています。
記事を読んでいる方に向けたメッセージ
藤本摂浩澪さん:興味をお持ちでしたら、お気軽に無料体験に参加してください。
伝統文化だからといって、必要以上に気構える必要はありません。
『習う』というよりむしろ『仲間になる』という感覚で来ていただければと思います。
伝統芸能を、日常に寄り添い、生活を豊かにするものとして、これからも伝えていきたいと考えています。