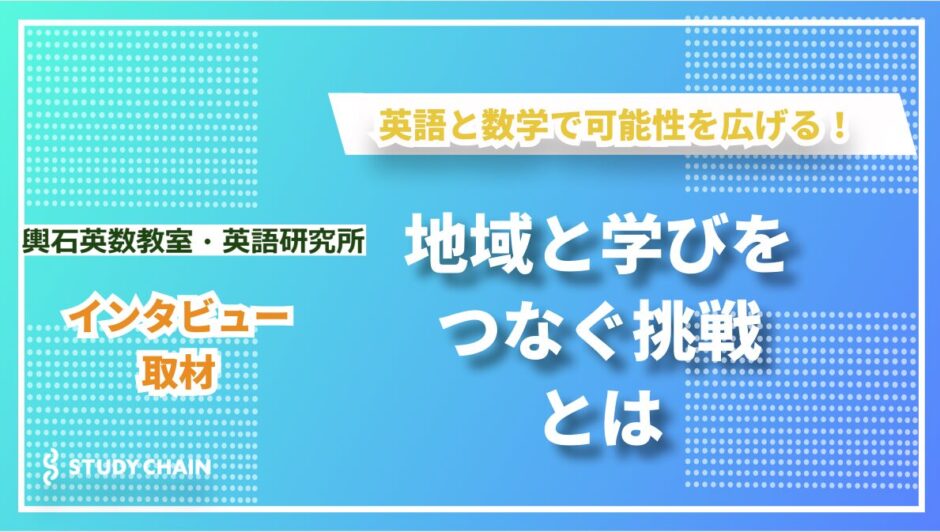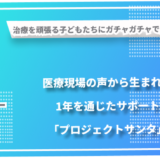山梨県で中学生・高校生を対象に個別指導を行う輿石英数教室。塾長の輿石氏は、生徒一人ひとりの学びのペースや希望に応じた柔軟なカリキュラムを提供し、英語や数学の苦手を克服するお手伝いをしています。一対一の徹底した指導スタイルを基本とし、生徒が「できるかも」と思える瞬間を大切にした教育が特徴です。
また、観光ガイド向け英語プログラムや社会人の再学習支援など、地域に根ざした多彩な活動も展開中。「勉強が苦手な子たちに寄り添い、自信を持ってもらいたい」という輿石氏の熱意が、長年多くの生徒の成長を支えています。教育への思いとこれからの展望について詳しく伺いました。
塾の概要と指導方針について
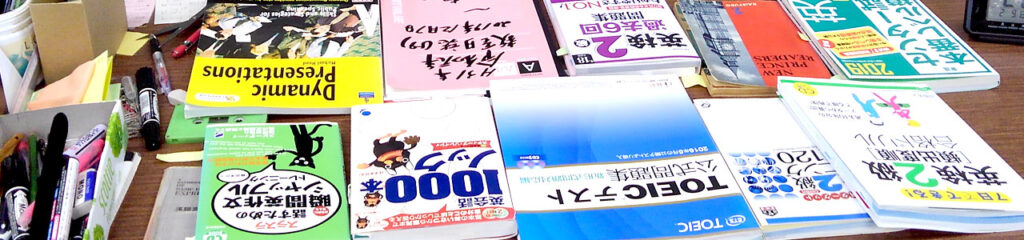
ー輿石英数教室では、どのような指導を行っているのですか?
輿石英数教室代表 輿石さん(以下敬称略):輿石英数教室は中学生と高校生を対象に、英語と数学を教えています。英語は幅広く指導していて、英会話から試験対策まで、生徒の希望に合わせた内容にしていますね。数学のほうは中学生が中心で、基礎的なところを補う授業が多いです。
また、基本的には1対1で教えています。1対1だと、生徒のペースや希望にしっかり応えられるのです。その場その場で、必要な内容に変えていける柔軟さがありますね。たとえば、今日は文法の予定だったけど「先生、テストがあるからこっちを優先してほしい」なんてリクエストがあれば、それに合わせて進めます。
それから、出張講座もやっています。県の産業技術団体や技能専門学校なんかで、観光ガイド向けの英語プログラムや、就業支援センターでの講座も担当してます。社会人の方が「やり直し英語」を勉強する場ですね。生徒さんや依頼主の要望に応じて、授業内容を考えています。
塾を始めたきっかけ
ーこの塾を始められたきっかけを教えてください。
輿石さん:私は、1993年まで山梨県の県庁で働いていたのです。その最後の2年間、アメリカのアイオワ州に派遣されていました。山梨県とアイオワ州は姉妹州なのですが、その交流事業を進めるために行きました。高校や大学を姉妹提携でつなげたり、地域同士の交流を促進するような仕事です。
この経験がすごく楽しくて、やりがいがありました。現地で英語を使って、多くの人と交流して。それで帰国してからも、こうした国際交流を支える仕事をしたいと思ったのです。ただ、続けるには資金も必要ですし、長くできる形を考えた結果、自分で塾を始めることにしました。
輿石英数教室では、生徒たちに英語を教えるだけじゃなくて、英語を使って新しい可能性を見つけてもらえたらなと思っています。
他塾にはない特徴と強み
ー輿石英数教室の特徴や強みを教えてください。
輿石さん:やはり1対1の個別指導ですね。輿石英数教室では基本的に、先生1人に対して生徒1人。これだと、生徒のペースに合わせて教えられるのです。例えば、予定していた内容をその場で変更してテスト対策に切り替えたり、得意な部分をもっと深掘りしたり。こういう柔軟さがあるのが個別指導の良さですね。
もう一つは、勉強が苦手な生徒さんをどうやってやる気にさせるかというところです。優秀な生徒さんももちろん大事なのですが、輿石英数教室はどちらかというと「勉強が苦手で困っている」子たちに寄り添いたいと思っています。そういう子たちが少しでも「できるかも」と思える瞬間を増やしたいのです。
指導方針と意識していること
ー指導する際に特に意識していることはありますか?
輿石さん:英語は、将来的に生徒が英語を楽しく使えるようになることを意識しています。ただテストの点数を上げるだけではなくて、英語を話すこと、聞くことに興味を持ってもらいたいのです。時間はかかりますけど、発音やリスニング、スピーキングの練習に力を入れています。
数学は、興味を持たせることが一番ですね。数学が苦手な子は「なんでこんなことやるの?」と思ってる場合が多くて。なので、なるべく身近な例を使って説明したり、楽しく学べるような工夫をしています。
提供しているコースとプラン
ー具体的なコースやプランについて教えてください。
輿石さん:中高生向けには、学校の授業に合わせた補習や、入試対策の授業をやっています。英会話の練習がしたいという生徒さんにも対応していますよ。
大人向けには、観光ガイド向けの英語プログラムや英検・TOEIC対策も提供しています。たとえば、観光名所を英語で説明できるようにするために、簡単な英語の原稿を作って、実際にプレゼンの練習をしたりもします。
どのコースも生徒さんや依頼主の希望に合わせてカスタマイズできるのが特徴ですね。
今後の展望
ーこれからさらに力を入れていきたいことは何ですか?
輿石さん:今後も、生徒一人ひとりのニーズに応じた柔軟な対応を続けていきたいですね。特に、勉強が苦手な子たちに寄り添って、「勉強が楽しい」と思える瞬間を増やしたいです。それと、地域での国際交流をもっと支える形も模索していきたいと思っています。