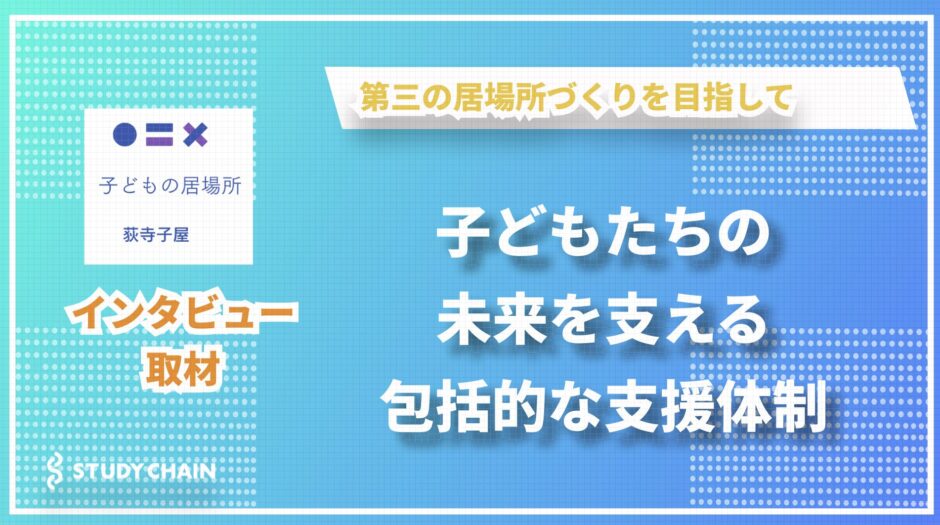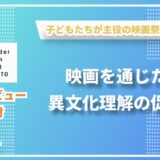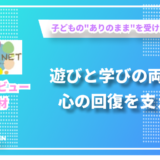静岡県伊東市で数年前から学習支援活動を展開し、現在では50名以上の子供たちへの学習支援と90名以上の子供たちに食事提供、210名以上の子どもたちへのフードパントリー支援を行う任意団体「荻寺子屋」。経済的な課題を抱える家庭の子どもたちに寄り添い、学習面での遅れを取り戻すサポートから、居場所づくり、生活支援まで、包括的な支援を提供しています。総務・事務方全般をご担当の加藤氏に、活動への想いと今後の展望についてお話を伺いました。
子どもたちの未来を支える包括的な支援体制
ー御社の概要について、どういった方を対象にどういった支援を提供されているのか、詳しく教えてください!
加藤:私たちの活動は、数年前に取り組み始めたある地区の小学生を対象とした学習支援からスタートしました。当初は純粋な学習支援として始めましたが、活動を進める中で、支援を必要としている子どもたちの背景にある様々な課題が見えてきました。特に学力面で遅れが見られる子どもたちを中心に支援を行っていますが、単なる学習支援にとどまらない包括的なサポートの必要性を強く感じています。
現在の支援内容は、学習支援を軸としながら、お弁当の提供やフードパントリーによる食品・生活用品の配布など、生活面でのサポートも行っています。特徴的なのは、支援を受けている子どもたちの約60%以上がひとり親家庭や多子家庭の子どもたちだということです。経済的な理由で学習塾に通えない、または十分な教育支援を受けられない子どもたちが中心となっています。
2月からは新たな取り組みとして、特に支援が必要な高学年の子ども10名程度を対象に、週2回の国語・算数の集中支援を開始する予定です。中には小学校2年生レベルの学習内容から始める必要がある子どもたちもいますが、一人ひとりの状況に合わせて、着実に学力を伸ばしていけるよう支援していきたいと考えています。
地域との出会いから始まった支援活動
ー加藤さんがこの支援活動を始められたきっかけについて教えていただけますでしょうか?
加藤:私は東京から伊東市に移住してきた70代半ばの人間です。移住後、社会福祉協議会を通じて荻地区を紹介され、漠然とではありましたが、地域の子どもたちと関わっていきたいという思いを持っていました。
この地区には以前、青少年育成会議という組織があり、お祭りの開催や子どもたちの学習支援などを行っていました。しかし、高齢化と少子化の影響で組織としての活動は消滅し、わずかな方々が細々と活動を続けている状況でした。そこで活動されている方々との出会いが、現在の支援活動を始めるきっかけとなりました。
活動を始めてみると、多くの子どもたちが基礎的な学習面で困難を抱えていることが分かりました。本を読むことができない、基本的な計算ができないなど、義務教育を受ける上で必要不可欠な基礎学力が身についていない子どもたちの存在を目の当たりにし、何とかしなければという強い思いを抱くようになりました。
大規模な支援体制と子どもたち一人ひとりに寄り添う姿勢
ー他の支援団体と比べて、特徴的な点や強みについて教えてください!
加藤:私たちの活動の最大の特徴は、支援規模の大きさにあります。現在、食事支援を受けている子どもたちが90名程度、フードパントリーによる支援では210名程度の18歳以下の子どもたちをサポートしています。このような大規模な支援体制は、他の支援団体からも驚かれることが多いです。
ただし、規模が大きくなる中で直面している課題もあります。特に学習支援においては、一定の質を確保することが重要です。小学生であっても、誤った内容を教えるわけにはいきません。子どもたちの理解度に合わせた適切な指導ができる人材の確保が、現在の大きな課題となっています。
第三の居場所づくりを目指して
ー子どもたちと接する際に特に意識されていることはありますか?
加藤:まず第一に意識しているのは、学習支援に集まる(60名ほどの)子どもたち全員の名前を覚え、子どもを信頼し、子どもたち一人ひとりを好きになることです。そうすることで子どもたちは初めて教える大人を信頼して距離をとらなくなります。名前を呼ばれることで、子どもたちは自分が認識され、大切にされていると感じることができます。
また、私たちの場所が「第三の居場所」となることを強く意識しています。支援を受けている子どもたちの多くは、家庭や学校において何らかの困難を抱えています。そのため、家庭でも学校でもない、安心して過ごせる場所として認識してもらうことが重要です。
特に、学校に対して苦手意識を持つ子どもたちが多いため、「学校臭さ」を出さないよう細心の注意を払っています。例えば、最初から決められた時間学習を続けることを強制せず、子どもたちの集中力に合わせて適度に休憩を入れたり、遊びの時間を設けたりしています。
学習支援においても、一人ひとりの理解度に合わせてゆっくりと進めることを心がけています。子どもたちの前に立ちはだかる壁は、一朝一夕に乗り越えられるものではありません。焦らず、じっくりと寄り添いながら、子どもたち自身が「分かった」「できた」という実感を得られるよう支援しています。
義務教育期間中の学力向上を目指して
ー今後の展望についてお聞かせください!
加藤:2月から始める週2回の学習支援は、次のステップに向けた大きなチャレンジで、試行錯誤を繰り返すことになると思っています。これまで40名程度の子どもたちを対象に学習支援を行ってきましたが、より効果的な支援を実現するため、特に支援が必要な子どもたち10名を対象に、きめ細かな学習支援を実施していく予定です。
この取り組みは、私たちにとってある種の「実験」でもあります。これまで支援してきた子どもたちの中には、中学進学後に高校進学を諦めてしまうケースもありました。義務教育期間中に必要な学力を身につけることができれば、子どもたちの将来の選択肢はより広がるはずです。どのようにすれば効果的に学力を向上させることができるのか、試行錯誤しながら最適な支援方法を見出していきたいと考えています。
ただし、このような活動を継続・発展させていく上で、時間と資金の確保が大きな課題となっています。現在は年間約500万円の費用がかかっており、寄付も徐々に集まってきているものの、まだまだ支援の輪を広げていく必要があります。
伊東市の世帯収入は2023年度で平均400万円と、全国平均の500万円以上と比べてもかなり低い水準にあります。このような構造的な課題を私たちの活動だけで解決することは難しいですが、できる範囲で子どもたちの未来をサポートしていきたいと考えています。
子どもたちが明るく学校に通い、社会に出ても必要な学力を身につけられるよう、これからも地道な支援を続けていきたいと考えています。支援の輪が広がり、より多くの子どもたちの未来を支えることができれば、この上ない喜びです。